※新しい情報を入手したため、2026年1月8日に内容の修正を行いました。
「スカイレスト ニューむろと」の歴史・施設内容・現地レポはこちら!!
「「スカイレスト ニューむろと」歴史・施設内容・現地レポ-2024年8月訪問」
「スカイレスト ニューむろと」の営業当時の看板はこちら!!
「「スカイレスト ニューむろと」今も残る営業当時の看板-2025年3月訪問」
こんにちは。
今回は、「スカイレスト ニューむろと」という、高知県室戸市に存在する廃墟について考察していきます。
概要

出典:2024年8月筆者撮影
1972年(昭和47年)7月18日に開業した「スカイレスト ニューむろと」は、レストラン・宴会場・結婚式場などを備えた複合施設として建てられました。
総工費は、当時の金額で1億2000万円です。
開業から6年後の1978年(昭和53年)ごろに閉業し、現在は廃墟として現存しています。
考察
「スカイレスト ニューむろと」は、独特な外観と圧倒的廃墟感から全国的に有名な廃墟です。また、心霊トークで有名な「稲川 淳二」さんが実際に足を運んで紹介したこともあり、心霊スポットとしても知名度が高いです。
ですが、営業期間が6年ほどと短いこともあり営業時の情報が乏しく、当時の様子を記録した写真や映像も全くと言っていいほど確認できません。そのため、全国的に有名な廃墟でありながら営業時の情報がほとんど無い、謎が多い施設として認知されています。
ネット上では短い営業期間や閉業した理由について、事件や事故が起こったからではないかという噂もあります。
このブログでは「スカイレスト ニューむろと」の閉業理由や設計など様々な謎について、資料を基に考察していきます。
この場所に建設された理由
「スカイレスト ニューむろと」が建つ室戸岬山頂は、室戸市中心部や室戸岬突端部から距離があり、アクセスや利便性が良い場所とは言えません。にもかかわらず、この場所に建設された理由は、近い将来に室戸岬山頂が開発されることを想定していたからです。
昭和47年7月16日発行の高知新聞には、「展望レストラン完成 初の民間企業進出 すばらしいながめ」という見出しの記事があります。記事には室戸岬山頂開発に関する記載があり、「市としては岬突端部は旅館街の移転も含めて景観の復活と保持、山上と周辺は開発歓迎の意向で、こんどの民間企業初進出を喜んでいる」とあります。
このことから、室戸市としては室戸岬突端部にある旅館を移転させて自然な景観を復活させ、室戸岬山頂の開発を望んでいることが分かります。
実際、1970年(昭和45年)に「室戸スカイライン」が完成した後、山頂には「国民宿舎むろと」や観光協会直営の売店が完成し、開発の形が出来つつありました。そして1972年(昭和47年)に「スカイレスト ニューむろと」が完成し、今後の室戸岬山頂の発展が期待されました。
将来は岬突端部の旅館が山頂に移転するほか、ゴルフ場・海洋科学センター・天文科学館・山麓と山頂を結ぶリフトなどの大規模な開発計画がありました。しかし「スカイレスト ニューむろと」の完成以降、山頂は開発されず、現在に至ります。
山頂が開発されなかった理由は、ブログ内の「閉業した理由」で詳しく述べています。
想定していた役割
「スカイレスト ニューむろと」は、室戸岬の新しい名所として「室戸スカイライン」の中心施設およびドライブインのような役割を担う想定でした。
1970年(昭和45年)に開通した「室戸スカイライン」は、開通後1年が経過しても山頂に注目されるような名所や大型施設がありませんでした。そのような状況の中、「スカイレスト ニューむろと」は様々な設備や機能をそろえた待望の名所として建設されたのです。
山頂に何もないからこそ、休憩する人のためのトイレや展望台、レストランやお土産売り場が求められていたのではないでしょうか。
結婚式場や宴会場については推測ですが、「スカイレスト ニューむろと」の運営会社が室戸岬の海岸沿いでホテルを経営していたため、関連して利用するために結婚式場や宴会場を作った可能性があります。
もしくは、山頂に新しい名所や移転してきたホテルが建設された際に、結婚式場や宴会場が求められると想定してのことだったのかもしれません。
「足摺海底館」をライバル視
先ほど、ブログ内の「この場所に建てられた理由」で引用した昭和47年7月16日発行の高知新聞には、「西の竜串の海中展望塔に負けじと、東の室戸岬に山上展望レストランが十六日オープンする」とあります。
記事にあるように、1972年(昭和47年)7月に東の室戸で「スカイレスト ニューむろと」が完成する半年ほど前、1972年(昭和47年)1月に西の足摺(正確には竜串海岸)に「足摺海底館」という海中展望塔が完成しました。

出典:2025年3月筆者撮影
「足摺海底館」は海上7メートルの高さに展望部分が十字に張り出しており、「スカイレスト ニューむろと」と展望部分の構造が似ています。東西でどちらも岬が近いという立地、そして完成時期と構造が似ていることから互いにライバル視していたのでしょう。
独特な設計の理由

出典:2024年8月筆者撮影
「スカイレスト ニューむろと」は高さ17メートル、直径3.5メートルの柱3本から1階と3階が3方向に張り出し、2階部分が吹き抜けとなっている独特な設計の構造をしています。
独特な設計の理由について、ブログ内の「この場所に建てられた理由」で引用した昭和47年7月16日発行の高知新聞によると、自然公園法規制区域のため、美観保持の観点から設計が再三変更されたことが書かれています。
記事には建物の設計に関して記載があり、「直径三・五メートルの三本の支柱を十七メートルも伸ばし、風の強いことを勘定に入れ二階部分を吹き抜けにした変則三階建て。一、三階は三方に張り出し岬方面はもとより、徳島や高知の海岸線など緑と青のすばらしい景色が楽しめる。」と書かれています。
このことから、特徴的な外観は自然保護法による美観保持と強風対策を考慮した結果であることが分かります。
「「スカイレスト ニューむろと」の歴史と現地レポ-2024年8月訪問」で「スカイレスト ニューむろと」は「鉄骨鉄筋コンクリート造」ということが判明しました。3本の柱のみで展望部分を支えることと、強風に耐えることを考慮して頑丈に作られているのでしょう。
展望部分の外壁だけが朽ちた理由

出典:2024年8月筆者撮影
この写真を見て分かるように、張り出した展望部分の外壁だけが剥がれ落ち、周囲と比較して脆弱な部分であることが分かります。
この要因は、中央の柱にかかる負担を軽減するために展望部の外壁を軽量に設計したため、その部分だけが脆弱となってしまい、周囲より朽ちてしまっているからだと考えます。また、張り出している構造上、潮風や強風の影響を受けやすいということも大きな要因です。
中央の柱から離れた外壁部分を重量のある鉄骨やコンクリートで設計すると、中央の柱にかかる負担が増加します。そのため、展望部分の外壁は軽量に作る必要があったのではないかと考えられます。
大砲のような排気フード

出典:2024年8月筆者撮影
「スカイレスト ニューむろと」には、柱の一番上部に大砲のような突起が1柱につき3か所あります。
この突起は換気口の排気フードです。排気フードを水平方向で大砲のような形状にすることで雨風が入りにくくなります。また、コンクリート製にすることで耐久性と統一感をもたせることができます。
柱の上部に換気口が必要だった理由は、換気と火災時排煙のためだと考えられます。
「スカイレスト ニューむろと」は、3つの柱の内部に、それぞれ1階から屋上まで螺旋階段がつながっています。螺旋階段の中心部には柱がないため、螺旋階段部は1階から屋上まで吹き抜けのようになっています。
換気としては、窓を開けなくとも常時換気ができるよう柱の上部に換気口が設置されたのではないでしょうか。
火災時には、どの階で火災が起こったとしても自然と螺旋階段を通じて最上階の排気口から煙が排出されるようにしていると思われます。
閉業した理由
「スカイレスト ニューむろと」は1972年(昭和47年)7月18日に開業しました。しかし、開業から6年後の1978年(昭和53年)ごろに閉業しました。
閉業の正確な理由は不明です。
ですが、以下の3つが有力な要因であると考えられます。
「室戸スカイライン」利用者減少による山頂開発の頓挫
おそらく、これが閉業の一番の要因です。
記事前半で述べたように、「室戸スカイライン」の完成によって国民宿舎や売店が建設され、室戸岬山頂が開発されつつありました。「スカイレスト ニューむろと」はそれに続く新名所となると同時に、室戸岬山頂へ初の民間企業進出でした。
室戸市としても、初の民間企業進出である「スカイレスト ニューむろと」を歓迎しました。今後も民間企業による名所の建設や、室戸岬突端部の旅館が山頂へ移転することを想定し、将来の山頂開発を期待していました。このように「スカイレスト ニューむろと」は、室戸岬山頂の開発を見越して建設されたのです。
しかし「スカイレスト ニューむろと」の完成以降、山頂は開発されず、新しい名所が完成することも、室戸岬突端部の旅館が移転することもありませんでした。
開発計画が頓挫した理由は、「室戸スカイライン」の利用者数が想定を大きく下回ったからです。(詳しくは、ブログ内「深堀コーナー」の「「室戸スカイライン」の利用者数について」をご覧ください)
1970年(昭和45年)に有料道路として開通した「室戸スカイライン」は、全線開通していないことや、開通後1年以上も山頂に大型施設がなかったこともあり、開通当初から想定より利用者数が少ない状況が続いていました。その後、山頂に「国民宿舎むろと」や「スカイレスト ニューむろと」といった大型施設が完成、1975年(昭和50年)には「室戸スカイライン」が全線開通しました。
ですが、「室戸スカイライン」は1973年(昭和48年)から発生した「オイルショック」の影響を強く受けていました。そのため、山頂に大型施設を完成させて全線開通したものの客足は増えず、利用者数は減少の一途をたどりました。
「室戸スカイライン」は通行料で建設費を補填する想定だったため、累積赤字だけが増加しました。
この状況では、高知県も室戸市もこれ以上開発をする余力などありません。民間企業としても、このような場所の開発を行うメリットがありません。室戸岬突端部の旅館も、あえて人が来ない場所へ移転することはしないでしょう。
このように、「室戸スカイライン」の利用者数が想定を大きく下回ったことにより開発計画は頓挫しました。「スカイレスト ニューむろと」は山頂開発の見通しを大きく誤ってしまったからこそ、6年という早さで閉業を決定したのだと考えられます。
オープン当初からの赤字経営
先ほど述べたように、1970年(昭和45年)に開通した「室戸スカイライン」は、開通当初から利用者数が想定を大きく下回っていました。
「スカイレスト ニューむろと」は、1970年(昭和45年)の「室戸スカイライン」開通前から計画・用地確保が行われていました。(詳しくは、ブログ内「深堀コーナー」の「「スカイレスト ニューむろと」の計画・用地確保について」をご覧ください)
ということは、計画段階では「室戸スカイライン」の想定利用者数から、「スカイレスト ニューむろと」の想定利用者数を計算していたはずです。「室戸スカイライン」の利用者が想定より少ないということは、必然的に「スカイレスト ニューむろと」の利用者数も想定より少なくなるということです。そのため、オープン当初から赤字経営となっていたと考えられます。
推測ですが、「スカイレスト ニューむろと」の長期滞在客は少なく、運営できるほどの収入を得ることが難しかったのではないでしょうか。展望台や休憩施設としての短期滞在利用はあったものの、大きな収入源であるレストランや結婚式場としての長期滞在利用がなく、売り上げが立たなかったのかもしれません。
「室戸スカイライン」の利用者が想定より少なかったため、「スカイレスト ニューむろと」の利用者も想定より少なくなり、オープン当初からの赤字経営を余儀なくされたと考えられます。
災害リスクによる安定した営業の難しさ
室戸岬は、台風銀座と呼ばれるほど台風が接近します。風を遮るものがない室戸岬山頂は、強風や台風による被害が大きく発生します。
また、室戸岬山頂を含めた室戸岬全体は、室戸層と呼ばれる崩れやすい頁岩(泥や微細な砂で構成された岩石)で構成されています。強い雨や台風が発生すると特に崩れやすく、実際「室戸スカイライン」の開通から10日の1970年(昭和45年)4月11日に土砂崩れが発生し、通行止めとなっています。
さらに、室戸岬は強い潮風が吹いています。室戸岬山頂に建つ「スカイレスト ニューむろと」は建物の高さもあり、常に潮風にさらされています。
推測ですが、頑丈に設計されているとはいえ潮風や強風による建物へのダメージが大きく、頻繁な補修が必要だったのではないでしょうか。また、時には台風や土砂崩れによる休業があったのかもしれません。
室戸岬山頂が災害リスクの高いエリアであるうえに、「スカイレスト ニューむろと」の建物の高さも関係し、安定した営業が難しかったのではないかと考えられます。
深堀コーナー
「室戸スカイライン」の利用者数について
1970年(昭和45年)4月1日に開通した「室戸スカイライン」は、片道約3.8キロ(最御崎寺付近の料金所から津呂山山頂までは片道約1.9キロ)と、全線開通ではありませんでした。
ですが、開通した直後は若者によるマイカー・バイクブームと、室戸岬を山頂から一望できるという物珍しさもあって多くの利用者数がありました。しかし、わずか1年で利用者数は大きく減少しました。
1971年(昭和46年)4月13日の高知新聞には、「一日に平均百九十台 初年度は不本意な出足」という見出しで、開通後1年経過した「室戸スカイライン」のことが掲載されています。記事には、「この程度の売り上げだと一般諸経費を引いて県の計画の60パーセントぐらい」と書かれています。
全線開通前「室戸スカイライン」の利用者数が減少した原因について、以下のことが理由ではないかと考えられます。
全線開通前「室戸スカイライン」の利用者数が減少した理由
●短い区間でありながら、入る際も出る際も通行料金を徴収する「二重取り」
●全線開通ではなく山頂でUターンして戻るため、行きと帰りで風景に変化がない
●開通後1年経っても、山頂には小規模な売店と望遠鏡が設置されたのみで、注目されるような施設がない
1970年(昭和45年)の開通から5年後の1975年(昭和50年)4月1日、ようやく「室戸スカイライン」は全線開通しました。距離は片道約9.0キロ、(最御崎寺付近の料金所から室津交差点付近の料金所までは片道約7.1キロ)です。
全線開通したうえ、すで山頂には「国民宿舎むろと」や「スカイレストニューむろと」といった大型施設も完成しており、先ほど述べた利用者が減少した要因は解消されました。ですが、利用者が増加することはありませんでした。
その大きな要因は、1973年(昭和48年)に起こった第四次中東戦争による「オイルショック」です。「オイルショック」によりガソリン価格は高騰、国としても石油利用を節約するよう呼びかけました。
1976年(昭和51年)4月12日の高知新聞には、「やっと9万2545台 通行車両は予想の4割」という見出しで、全線開通後1年経過した「室戸スカイライン」のことが書かれています。1979年(昭和54年)12月29日の高知新聞には、「県営有料道路は借金まみれ 特に深刻な『室戸』」という見出しで、他の県営有料道路の中でも利用者が非常に少ない「室戸スカイライン」についての記事があります。
このように、全線開通後も利用者が増加することはなく、累積赤字だけが増えていきました。
「スカイレスト ニューむろと」の開業が遅れた理由について
「スカイレスト ニューむろと」は、1970年(昭和45年)の「室戸スカイライン」開通前から計画が行われ、用地も確保済みでした。ですが、開業したのは1972年(昭和47年)7月18日です。なぜ、計画・用地確保から開業まで2年もの期間が空いたのでしょうか。
その理由は、自然保護法の指定区域により、建物が景観を壊す恐れがあるとして、市や県からなかなか建設の許可が下りなかったからです。
建設の許可が下りるまで何度も建物の設計を変更し、ようやく認められました。
また、建物の外観はもちろんのこと、建物の色や周辺への影響にも配慮するよう指示がありました。そのため、建物の色に関しては運営会社・設計担当者・県の自然保護課が協議のうえ、最適な色を選びました。周辺の影響に関しては、室戸岬山麓である室戸岬町の高岡地域へ土砂を流出させないことが条件でした。
このように、「スカイレスト ニューむろと」の計画・用地確保といった動きは早かったものの、建設の許可が下りるまでに時間がかかってしまったのです。
推測ですが、計画・用地確保後、すぐに建設の許可が下りていれば「室戸スカイライン」の客足が遠のく前に完成し、人気スポットとなっていたかもしれません。
まとめ
以上が、「スカイレスト ニューむろと」の閉業理由や設計などの考察です。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
よろしければ以下の関連投稿もご覧ください。
「スカイレスト ニューむろと」の歴史・施設内容・現地レポはこちら!!
「「スカイレスト ニューむろと」歴史・施設内容・現地レポ-2024年8月訪問」
「スカイレスト ニューむろと」の営業当時の看板はこちら!!
「「スカイレスト ニューむろと」今も残る営業当時の看板-2025年3月訪問」

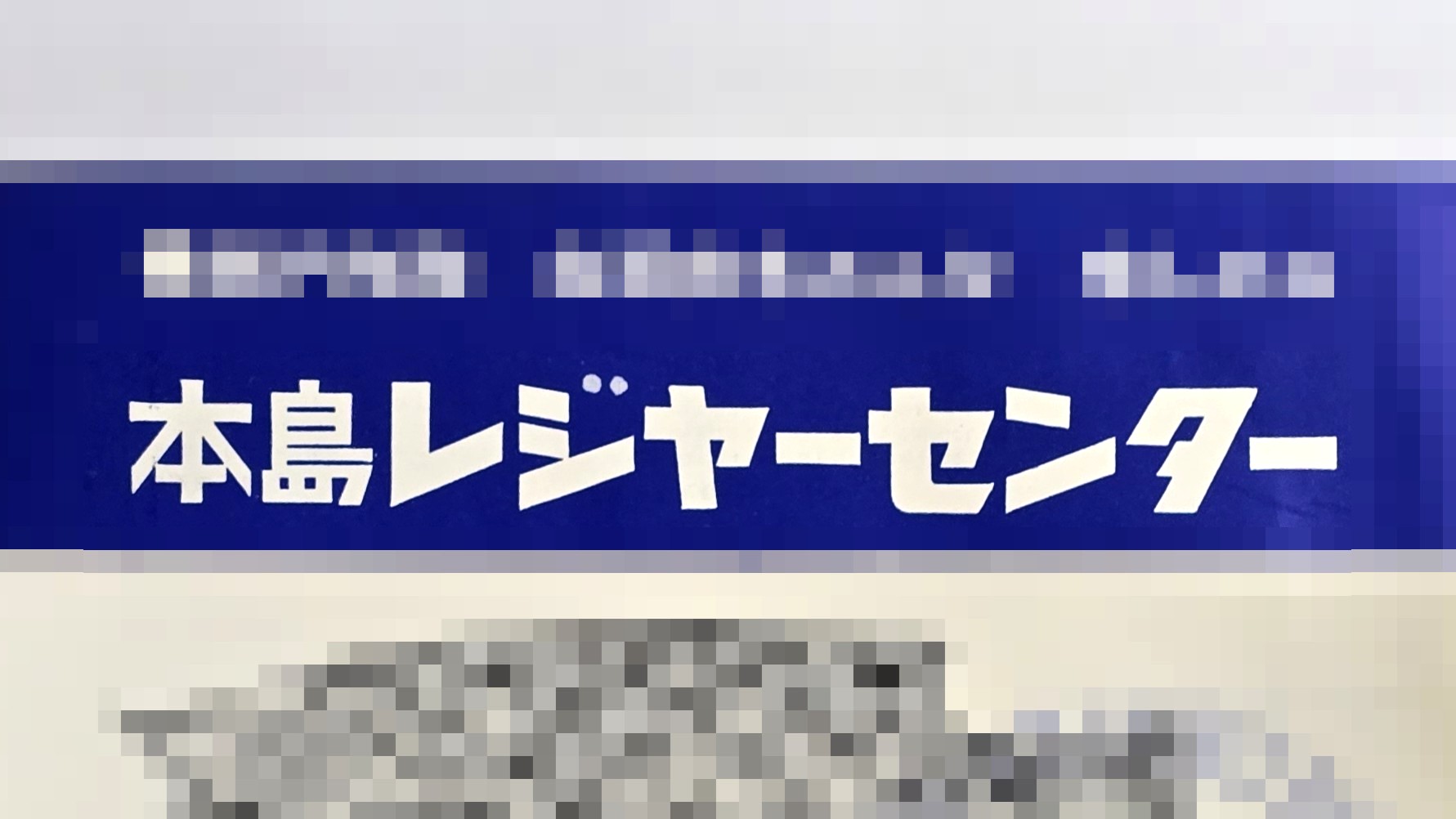
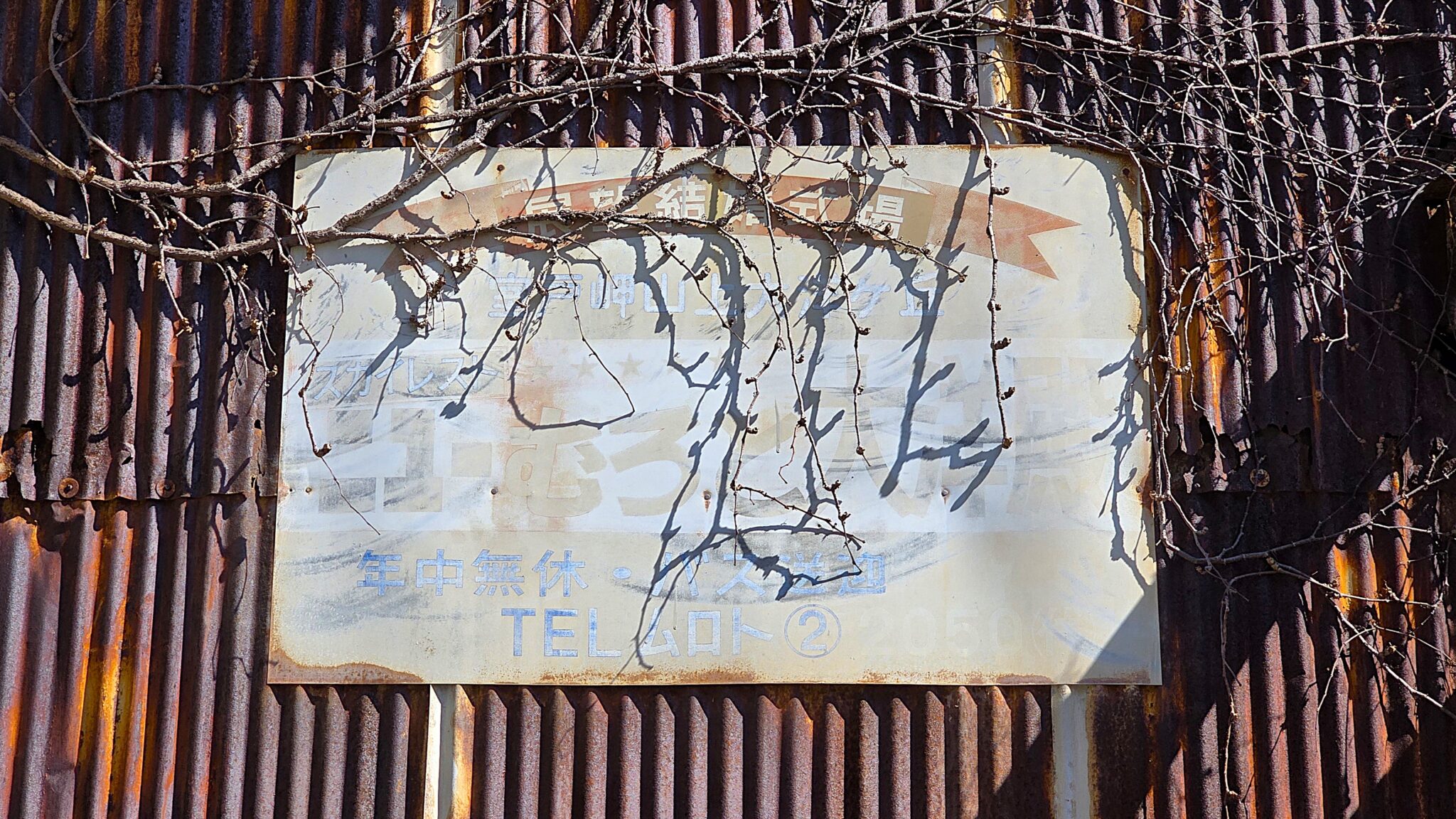
コメント