こんにちは。
今回は、高知県香美市土佐山田町の鍾乳洞内で栽培されていた「イオン菜」という野菜について調査していきます。
概要
「イオン菜」は、高知県香美市土佐山田町若宮の鍾乳洞で栽培されていた野菜です。
土佐山田町若宮にある龍馬洞(郷朧洞)という鍾乳洞の中で、大根の種子を発芽させた野菜(かいわれ大根のようなもの)を栽培していました。
栽培をしていた運営団体は「とさ若宮国民レジャーセンター」です。理事長を務めていたのは、K氏という人物です。K氏は、のちに「イジメもやまる日本発祥の地」の運営を行っています。
「イジメもやまる日本発祥の地」についてはこちら。
「【高知県香美市】「イジメもやまる日本発祥の地」とは何だったのか-2025年2月記述」
「イオン菜」という名前の由来は、鍾乳洞内のマイナスイオンの影響を受けて、特殊な栄養素が含まれているというイメージから付けられました。
この「イオン菜」は、K氏が代表を務めていた「若宮高原ユースホステル」で提供されていたほか、東京のデパートに空輸されて販売されていました。
栽培に至った経緯
K氏は、レジャーセンターの経営が苦しくなったため、何か観光資源はないかと鍾乳洞に入ってみたところ、長さ70センチほどのキノコのようなものが生えているのを発見しました。
それを見て、鍾乳洞内で野菜類が栽培できるのではないかと考えました。そこで鍾乳洞内の温度を調べてみると、年中15度と湿度57%前後で、野菜の発芽に必要な気象条件であることが分かりました。
そこで、昭和40年10月中旬ごろ、試しに岩の間の砂地にダイコンの種をまいてみました。すると、5日ほどで約10センチまで成長しました。
刺身のツマやお吸い物に入れて試食したところ、少し風変わりな味がするものの、生鮮野菜が少ない日などには十分代用できることが分かりました。
また、鍾乳洞内には健康に効果のあるマイナスイオンが多いことから、ここで野菜を栽培すると特殊な栄養素が含まれるようになるのではないかと考えました。
本格的に量産をするため、鍾乳洞内の砂地だけでなく、岩の上など330平方メートルで栽培を始めました。
販売先
昭和40年、初めにK氏が代表を務めていた「若宮高原ユースホステル」で観光客に提供をしたところ、珍しさもあって好評でした。
昭和43年ごろ、大阪に出荷してみましたが不評でした。
昭和44年、K氏が東京に訪れた際、日本交通公社の社員に食べてもらったところ「東京の好みにぴったり」と絶賛され、昭和44年7月11日から東京日本橋の三越デパートで即売会を開催することになりました。
販売期間
正確な販売期間は不明です。
昭和40年12月6日発行の高知新聞「鍾乳洞の中で野菜作り-若宮に風変わりな観光資源」では、「イオン菜」を本格的に栽培を開始し、「若宮高原ユースホステル」で観光客に提供をしていることが書かれています。
昭和48年7月20日発行の高知新聞「夏休みツアー・ガイド 脱公害 イオン空気」では、「若宮高原ユースホステル」で「イオン菜」を使って「イオンなべ」や「イオンずし」が提供されていることが書かれています。
これ以降、「イオン菜」に関する記事や情報は見つかりませんでした。
少なくとも、昭和40年から昭和48年までは販売されていたようです。
栄養素
記事によると、ビタミンCや消化酵素が大量に含まれているとあります。
参考資料
高知新聞「鍾乳洞の中で野菜作り-若宮に風変わりな観光資源」(昭和40年12月6日発行)
高知新聞「イオン菜 東京へ進出-新名物に 鍾乳洞内で栽培」(昭和44年7月11日発行)
高知新聞「夏休みツアー・ガイド 脱公害 イオン空気」(昭和48年7月20日発行)
まとめ
以上が、調査をした「イオン菜」の内容です。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。


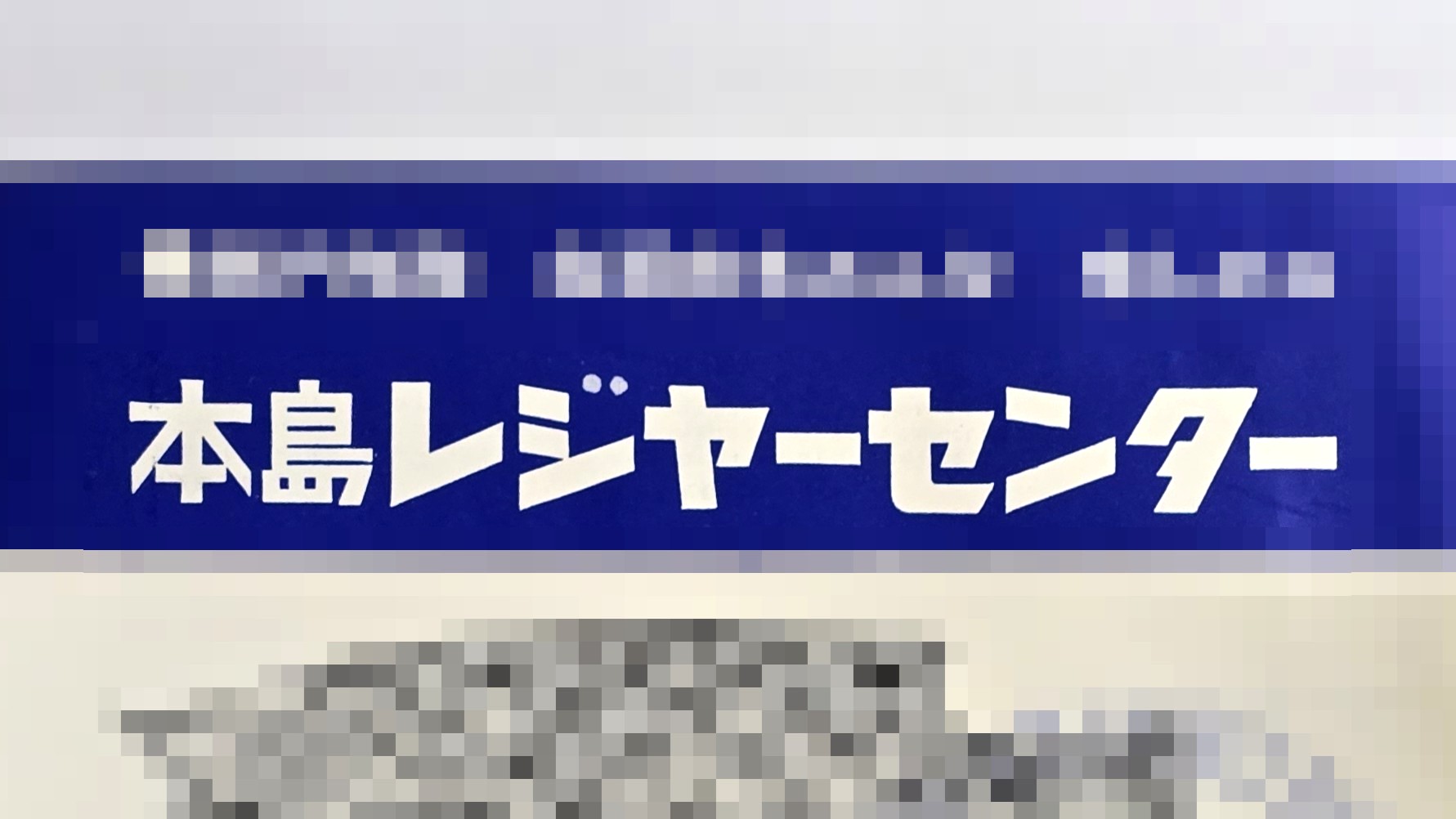
コメント